オンラインゲームでイライラ『もう一人の自分』が現れる心理的メカニズム
こんにちは。スタジオイオタ(studio iota LLC.)代表の前田紗希です。
ちかごろ、オンラインゲームをやってる方も多いと思います。私もそのひとりです!
仲間と協力して勝利を目指すはずが、プレイ後にはぐったり疲れていたり、
むしろゲームをやる前よりストレスが溜まってイライラしている…
そんな体験、ありませんか?
そんなゲームにまつわる少し真面目な話を、音楽療法の専門家が分析してみようと思います。
特に若い世代を中心に人気の、無料で遊べるMOBA系ゲーム(チーム対戦型オンラインゲーム。
手軽に楽しめるはずなのに、
プレイ後に強い疲労感やストレスを感じるという声を聞くことが多いんです。
ときには、プレイ中に他人に対してイライラしたり、
自分のミスに落ち込んだり…。
これは、ただのゲームのやりすぎで片付けていい問題なのでしょうか?
今回は、そんなゲームで心がすり減る仕組みについて、
心理学的な視点から少し掘り下げてみたいと思います。
前田 紗希(編集長) 作曲家、ドラマー、鍵盤奏者、RECエンジニア、音楽心理士。
国立音楽大学在学中にデビューし、その後、ロンドン、ベルリン、ニューヨークでの演奏経験を重ねる。25リットルのリュックとドラムスティックを携えて世界一周のち、旅・音楽・食を融合させるレコード会社「studio iota LLC.」を設立。
国内外で音楽家として演奏活動を行うのみならず、音楽療法士としても活動し、心理学の学位を取得。オウンドメディア4誌の編集長で「車中泊」コンテンツなど数々のSEO1位を生み出す。

なぜMOBAは「イライラ製造機」になりやすいのか?
期待の非対称性が生むストレス
まず結論から言うと、価値観の違う人たちが、無理やり同じチームに放り込まれるという構造的なズレ、
つまり「期待の非対称性」こそがストレスの原因です。
無料ゲームは参入のハードルが低いため、プレイヤーの目的もスキルもバラバラになります。
こうした人たちが一つのチームになると、何が起こるでしょうか。
- 競技志向の人:本気で勝ちたい ガチ勢
- 娯楽志向の人:楽しく遊びたい エンジョイ勢
- 初心者:まだルールがよくわからない
- 途中であきらめる人:やる気がなくなったら離脱する
基本的な戦術の無視や、突然の試合放棄といった行動が頻発し、
真剣にプレイしている人ほど、裏切られたような気持ちになってしまいます。
この瞬間に、私たちの心に最初の毒がじわじわと染み込んでくるのです。

「味方のせい」と「自分のせい」の無限ループ
帰属のエラー
その毒には、主に2つの形があります。
- なんで味方はそんなことするの?という苛立ち(=外的帰属)
- 自分がもっと上手ければ勝たせられたかもしれないという絶望(=内的帰属)
こうして、原因を他人と自分の間で行ったり来たりさせる「帰属のエラー」が繰り返されることで、
メンタルがじわじわ削られていきます。
この二重の負荷が、「ゲームをすると疲れる」正体のひとつ。
気づかないうちに、
心のエネルギーを使い果たしてしまっている
んですね。

オンライン空間で生まれる、もう1人の自分
理性の麻痺
普段は温厚なのに、ゲーム中になると「クソ!」とか「何やってんだよ!」など、
汚い言葉が口から出てしまうこと、ありませんか?
理性のスイッチが切れて、もう1人の自分が目を覚ます瞬間です。
これは「オンライン脱抑制効果」と呼ばれていて、次のような要因によって引き起こされます。
- 顔が見えない(匿名性)
相手も自分も顔が見えないと、「何を言ってもバレない」という気持ちが働きます。向こうに人間がいることを忘れがちになって、相手をキャラクターとして認識してしまう。「その向こうにも感情を持った人間がいる」という当たり前の事実が麻痺していくのです。
- すぐに反応が返ってこない(非同期性)
対面なら、相手の表情や声色から、あ、今のは言い過ぎたかな、と気づけます。しかしオンラインでは、そうした非言語的なフィードバックがありません。自分の発言がどれだけ相手を傷つけたか、感じにくくなります。
- 誰も叱ってくれない(権威の不在)
現実世界での先生や上司のような、自分の言動を律する存在がいないフラットな空間では、自分を抑える意識が働きにくくなります。攻撃性に歯止めがかからなくなるのです。
こうした条件が揃うと、人は驚くほど簡単に建前や社会的規範を外してしまうのです。
そう、ゲームの中であなたが暴言を吐いたあの瞬間。
それはあなたの本性というより、脳の理性を司る部分「前頭前野」が一時的に働きにくくなっていた状態、と言えるのかもしれません。

ゲーム中の攻撃的な自分は現実にもついてくる⚠️
負の神経可塑性
では、ゲーム中の攻撃的な自分は、現実の自分に影響を与えるのでしょうか。
ゲームの中だけの話だから大丈夫と思いたくなりますが、
問題は、ゲームの中で繰り返された「暴言でストレスを発散する」パターンが、
脳内で一種の「報酬回路」として記憶されてしまうこと(負の神経可塑性)です。
どういうことかというと、イライラするたびに暴言を吐くパターンが、
手軽なストレスの解消法として脳にインプットされてしまうのです。
そして、それが現実生活でも反射的に出てくるようになる可能性がある。
- すぐに口調が荒くなる
- ちょっとのことで誰かを責めたくなる
- 無意識に他人を見下すようになる
ゲームがあなたを凶暴に変えるわけではありません。
でも、ゲームの中で処理しきれなかったストレスや、
攻撃的な反応のクセが、
あなたの現実にも少しずつ染み出していくのです。

ゲームの主導権を握るのは、自分自身🧭
感情のハンドルを手放さないために
じゃあ、どうすればいいのか。
まずは「ちょっと今、自分イライラしてるな」と気づくだけでも十分です。
イライラが続くときは、一度ゲームから離れてみるのも良い方法です。
チャットをオフにしたり、気を遣わない友達とだけ遊んでみたり。
今日は勝った/負けた、より「楽しめたかどうか」に意識を向けるのも効果的です。
コントローラーを持ってるのは自分のはずなのに、
気づいたら感情に振り回されていた──
そんなときは、そっと手を離す勇気も大切かもしれません。(そうは言っても戦績があるものわかりつつ!)

最後に:ゲームに心を食われないために
ゲームは本来、楽しいもの。
日常をすこし豊かにしてくれる存在のはずです。
でも、そんなはずだったのに「自分が嫌いになりそう」と感じたら、
それはちゃんと立ち止まるサイン。
怒りや焦りに振り回されないために。
毒のケダモノを育てるんじゃなくて、ちゃんと自分と付き合っていくために。
ゲームと、少しだけ丁寧に向き合ってみるのもいいかもしれません。
▼ おまけ:こんな対策もおすすめです
- チャットをオフにする
- 気心の知れた仲間とだけ遊ぶ
- イライラしたら、そっと電源を切る勇気を持つ
- 勝敗よりも、自分が楽しめたかどうかを大切にする
今日は一人のゲーム好きとして、プレイ中に感じた心の動きや疑問を、
心理学の知見をヒントに整理(考察)してみました。
専門的な意見ではありませんが、「わかるかも」と共感してもらえる部分があればうれしいです!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
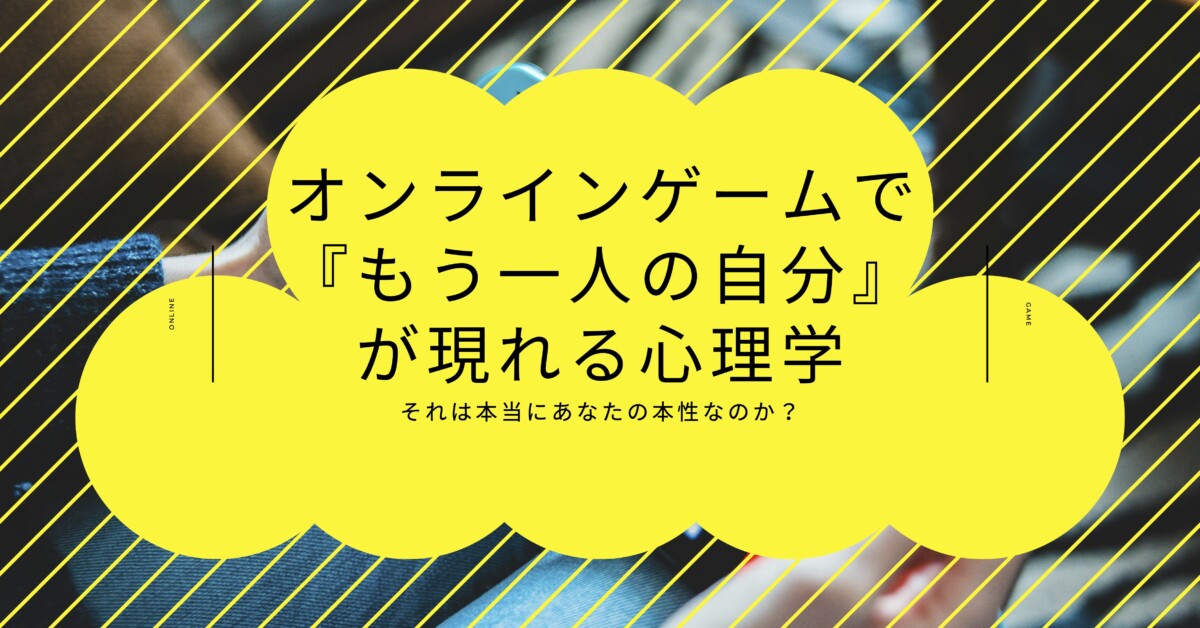
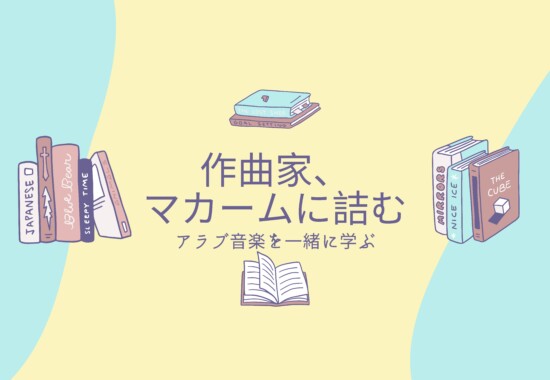


この記事へのコメントはありません。