音楽業界が注目すべきミュージックツーリズム|フジロックが示すこれからの音楽体験
こんにちは。スタジオイオタ(studio iota LLC.)代表の前田紗希です。
毎年、初夏の足音が聞こえてくると「今年のフジロック、どうする?」って会話、あちこちで聞こえてきませんか?
日本有数の音楽フェスティバル、FUJI ROCK FESTIVAL。
新潟県湯沢町の苗場スキー場には、国内外から何万人もの音楽ファンが集まります。
あの光景は、すっかり日本の夏の風物詩になりました。
誰と行くか、どのステージをどう回るか、
そして、どうやってあの苗場の地に辿り着くか——。
そう、私たちはいつのまにか、音楽を聴くために旅の計画を立てているんですよね。
でも、この巨大な音楽イベントって、いったいどんな力を持っているんでしょう?
今回は、まず数字で見るフジロックのすごさから始まって、
そこから見えてくる音楽の本当の価値や、
ミュージック・ツーリズム
について、少し掘り下げて考えてみたいと思います。
前田 紗希(編集長) 作曲家、ドラマー、鍵盤奏者、RECエンジニア、音楽心理士。
国立音楽大学在学中にデビューし、その後、ロンドン、ベルリン、ニューヨークでの演奏経験を重ねる。25リットルのリュックとドラムスティックを携えて世界一周を達成し、旅・音楽・食を融合させるレコード会社「studio iota LLC.」を設立。
国内外で音楽家として演奏活動を行うのみならず、音楽療法士としても活動し、心理学の学位を取得。オウンドメディア4誌の編集長で「車中泊」コンテンツなど数々のSEO1位を生み出す。

【第1部】 データで見る、フジロックのすごいインパクト
フジロックが地域にもたらす経済効果は、
チケット代×動員数みたいな単純な話ではありません。
実はそれをはるかに上回る規模になっています。
いくつかの調査によると、経済全体に与える影響は、
近年で約150億円から、多い年では230億円以上にものぼると試算されているんです。
チケット収入だけじゃない!その内訳って?
「経済効果」というと少し難しく聞こえるかもしれませんが、これは主に次の3つの要素で成り立っています。
- 直接効果
チケットの売上や会場での飲食、グッズ販売など、フェス運営から直接生まれるお金のこと。 - 一次波及効果
参加者が使う交通機関や宿泊施設、周辺の飲食店やお店などでの消費がもたらす効果。特に開催地の新潟県湯沢町にとっては、夏の観光シーズンを支える大きな力となっています。 - 二次波及効果
フェス関連の仕事で得た収入が、さらに他の消費に回ることで、地域経済全体が潤う循環。
この構造を見ても、フジロックが湯沢町という地域と一体となり、持続的な経済活動を生み出していることがよくわかります。

近年の動員数と経済効果を見てみると
コロナ禍で大変な時期もありましたが、フジロックの集客力はやはりすごいものがあります。
- 2019年(コロナ禍前)には、233億円超の経済効果が報告されています。動員数は前夜祭を含め13万人に達しました。
- 2021年は観客数を制限したものの、117億円の経済波及効果が見込まれました。
- 2015年の調査でも、約150億円の経済効果が試算されています。
- そして2024年は、4日間で約96,000人が来場。2025年には122,000人まで回復する兆しがあるとも言われています。
これらの数字を見ても、フジロックの持つ経済的影響力の大きさがよくわかります。
地域との連携が生み出す相乗効果
フジロックは単なる音楽イベントというだけでなく、開催地である新潟県湯沢町と深く連携して、地域経済の活性化に貢献しているんです。
例えば、ふるさと納税の返礼品にフジロックのチケットが含まれるなど、ユニークな取り組みも行われています。
こうした地域との良い関係が、イベントを一過性で終わらせず、息の長い経済効果へとつなげている理由の一つなのでしょう。

【第2部】巨大な経済効果の原動力は「文化」にある
これだけ大きな経済効果が生まれるのは、いったいなぜでしょうか。
その答えは、フェスティバルが単なるイベントではなく、
様々な思惑や熱量が渦巻く文化の発生装置であり、
それを育てる場所だから、
という本質的な価値にあるのだと思います。
「フェスが育む文化」とは、具体的にどのようなものでしょうか?
- 多様なカルチャーの融合
音楽フェスは、音楽を中心にファッション、アート、食、ライフスタイルといった様々なカルチャーが交差するプラットフォームです。
多すぎて、分身しないと間に合わないぐらいのコンテンツ量です。
参加者は日常から離れた空間で、新たな音楽や価値観に触れることができます。
- 真価が問われる、特別なステージ
フェスのステージは、誰もが立てるわけではない特別な場所。時代の潮流や業界の思惑も反映される場所だからこそ、キャリアを左右する覚悟のパフォーマンスが求められます。
そうしたアーティストの熱量がダイレクトに伝わるからこそ、ファンにとっては、それを五感で味わい、他の参加者と一体感や感動を分かち合える貴重な機会となります。
- コミュニティの形成
フェスは、共通の好きなものを持つ人々が集い、交流するコミュニティとしても機能します。このようなつながりは、イベントを一過性のものでなく、持続的な文化として根付かせる力になります。
- 文化的土壌の醸成
地方で開催されるフェスは、都市部に行かなくても最先端の音楽やアートに触れる機会を提供し、その土地の音楽文化が育つ土壌になります。
これをきっかけに、自分で音楽を始めたり、イベントを企画したりする人が出てくるかもしれません。

そもそも、私たちはなぜ、わざわざ旅費を払って、重たい荷物を背負ってまで、
自然の中で音楽を聴こうとするのでしょうか。
それはきっと、音楽がただ聴くものではなく、そこで生まれるすべてを体験するものだからなんですよね。
一瞬に賭けるアーティストたちの、覚悟のこもったパフォーマンス。
音楽を中心に、ファッションやアート、
美味しいフードが渾然一体となる独特の空気感。
日常から少しだけ離れた場所で、知らない誰かと音楽を共有する、あの特別な感覚。
こうした、ヒリヒリとした緊張感さえも含んだ本物だけが持つ文化的な魅力があるからこそ、
私たちは時間やお金をかけてでもその体験を求めます。
その巨大な熱量が、結果として大きな経済効果、つまり産業を生み出しているのです。

優れた文化が産業を育て、産業の力がまた新たな文化を創造する土壌となる。
この素晴らしい好循環こそ、フジロックが長年にわたって輝きを失わない理由であり、
音楽が持つ本質的な力を証明しているように感じます。
【第3部】音楽が「旅の目的」になる。ミュージック・ツーリズム
文化的な魅力は、私たちの行動をさらに能動的なものへと変えていきます。
それが、音楽を主目的に旅をするミュージック・ツーリズム(音楽観光)です。
そのスタイルはさまざま。
イギリスのグラストンベリー・フェスティバルのように巨大フェスが目的地になることもあれば、
アメリカのナッシュビルのように街全体が音楽の聖地として人々を惹きつける場所もあります。
そして日本には、自然と共にあるフェス文化の代表格として、フジロックがあります。
苗場でのフジロックには、あの場所でしか味わえない体験が確かにあるのです。
キャンプの過酷さ、台風大雨の経験、難民生活のようなシャワールームなどなど……笑

フェス好きの方はご存知の通り、苗場の天気はとても変わりやすく、快適な晴天から、装備がなければ心細くなるほどの豪雨に見舞われることも珍しくありません。
でも、不思議とあの場所にいると、音楽が、森の匂いや澄んだ空気、夜空の星々、そして時には激しい雨さえも、全てをひっくるめて特別な体験に変わっていく。
むしろ、困難を乗り越えるからこそ生まれる一体感や高揚感が、フジロックを唯一無二のものにしているのかもしれません。
まさに、こうした綺麗事だけではないリアルな体験こそが、「フジロックに行く」という行為を、単なるイベント参加ではない特別なデスティネーション(目的地)へと変えているのです。

都心の便利な会場とは全く違う、雄大な、そして容赦ない自然の中で開催れること
私たちがフェスで過ごす時間は、巡り巡って、次のような形で地域にプラスの効果を生み出しているのではないでしょうか。
- 滞在型観光の促進
数日間のキャンプイン形式のフェスは、自然と参加者の滞在時間も長くなりますよね。
キャンプ + 音楽フェス =キャンプフェス
音楽フェスに行ったことがある方なら分かると思いますが、1日楽しんだあと帰りたくないなと思ったことはありませんか?でも、キャンプフェスなら帰らなくていいんです!!
その分、周辺の宿やお店、飲食店も賑わい、地域にとっては大きな支えになっています。
- インバウンド観光の推進力
フジロックは海外での知名度も非常に高く、毎年多くの外国人観光客が訪れます。日本の音楽シーンだけでなく、日本の自然やおもてなしの心を体験する貴重な機会となり、質の高い国際交流の場として機能しています。
- 関係人口の創出
フェスをきっかけにその土地を訪れた人が、地域の自然や食、人の魅力に触れてファンになる。イベントの後も、また違う季節に訪れたり、特産品を取り寄せたり。地域との継続的なつながりを持つ関係人口が生まれることにも貢献しています。

おわりに
経済効果という大きな数字から、ステージに立つアーティストの覚悟、そして参加者一人ひとりのリアルな体験まで。
こうしてフジロックという一つの現象を様々な角度から見つめ直すと、音楽を届けることを仕事にしている私たちにとっても、本当に多くの発見があります。
音楽は、ただ誰かの日常の中で聴かれるだけでなく、こうして人を動かし、地域を元気にする力も持っている。
その事実に勇気づけられますし、音楽にはまだまだ知らない可能性がたくさん眠っているんだと、改めて気づかされます。
この記事が、次の旅を考えるささやかなきっかけになれば、とても嬉しいです。
またどこかの会場で、皆さんと良い音楽を共にできる日を楽しみにしています!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
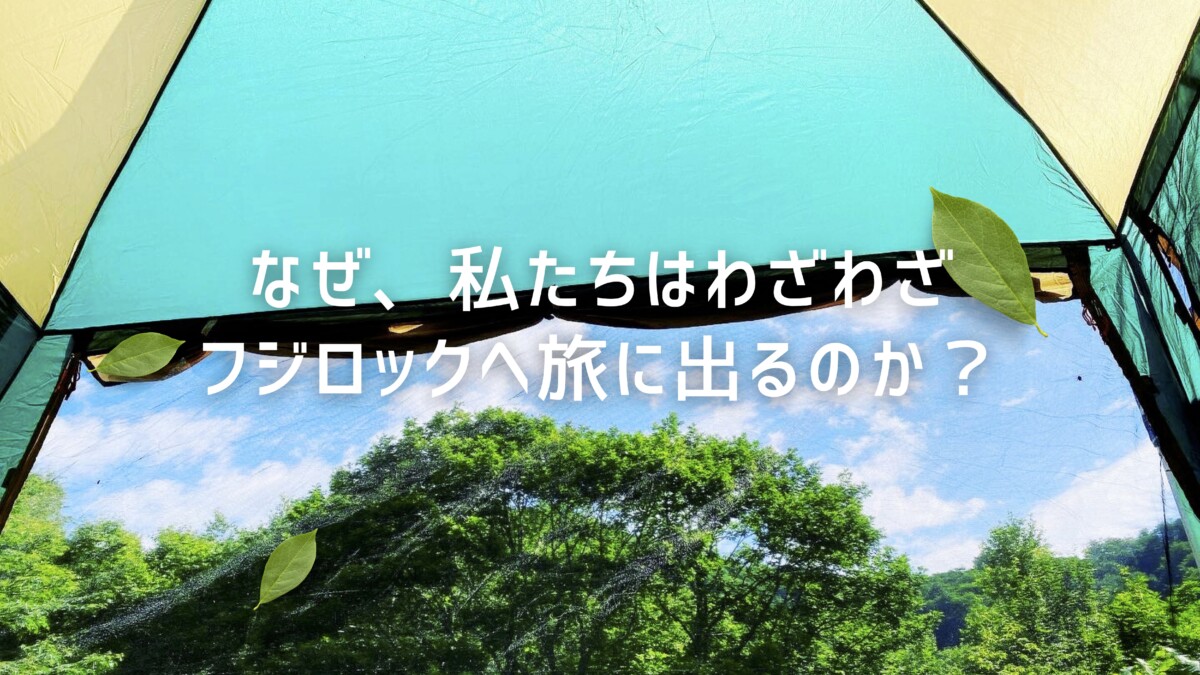
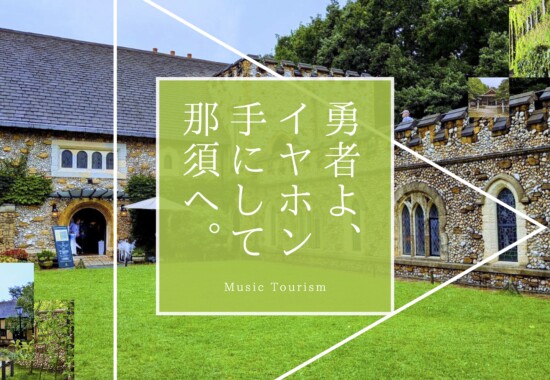



この記事へのコメントはありません。